コラム
落合憲弘
John Sypal
タカザワケンジ
なぎら健壱

著者が2003年〜2004年に四谷で運営していた「Days Photo Gallery」オープン時のチラシ
実際に場所のわかりやすさは大事で、いまのようにGoogleMapなどなかったので、ギャラリーで留守番をしていると、場所を訊ねる電話がよくかかってきた。誰もが番地と地図をすり合わせて訪ねてきたのだ。
私がやっていたギャラリーは新宿通りから100メートルほど入った路地の先だったのだが、路地の入り口までは辿り着くのだが、そこから先で迷う人が多発した。最初の頃は「路地を曲がって100メートルくらい」とか「1,2分」なんていう説明をしていたのだが、正確に100メートルというわけでないし、人は100メートルをはかって歩いているわけではないし、時間も同じくだ。よくよく考えてみれば1分と2分では倍の長さだ。だからだろう、路地の先までいってしまい(10分くらい先)、そこからまた電話がかかってきて「どこにもないんだけど!」となかば切れられたこともあった。

「Days Photo Gallery」オープン前の施工中の風景
いろんな説明の仕方を模索(というほど大袈裟なことではないが)して、結局もっとも正確に伝わるのは路地の入り口からは何件目ですという言い方をするのが有効だという結論をえた。お客さんは路地の入り口から数えながら進んでくるので、ほぼ間違えることがない。単純といえば単純な話だ。前置きがかなり長くなってしまったが、そんな経験からギャラリーに作品を観に行く際、どうしても借りる側の気持ちになって考えてしまうのだ。
この調査、研究を始めるに当たっての疑問はいくつかあるが、そのひとつは「何故、日本にだけ写真の自主ギャラリーは存在しているのか?」というもの。
70年代に自主ギャラリーを始めた若者の動機は、当時すでに存在していた複数のメーカー系ギャラリーには審査があって簡単に作品を発表できるわけではなく、カメラ雑誌でもまったくの無名では作品を掲載してもらうことは容易ではなかった。ゆえにそれらへのアンチとして自主ギャラリーが生まれたという経緯がある。
「自分たちだけの写真を発表するメディアを持つことが、若い写真家たちの唯一の社会への反撃であった。既成のメディア、マスコミを利用してきた権威主義的な主張の強い時代への反発ということもあり、閉ざされた空間を持ちえることが新たな写真を思考し、セグメントする場にもなっていた」「反メジャー指向の写真家たちのきわめて閉鎖的な、スイート・ホーム・ギャラリーでもあったのである」
(『インディペンデント・フォトグラファーズ・イン・ジャパン 1976-83』より)
ただ、時代をへて俯瞰してみると、そして多くの方にインタビューを繰り返すなかでひとつのことが浮き彫りになってきた。日本にカメラメーカーが集中し、世界の中で圧倒的なシェアを誇るという特殊な環境だ。結論からいうと、アンチであるはずの若い写真家もまたその恩恵に十分にあずかっていたという事実だ。
確かに「若い写真家たちの唯一の社会への反撃であった」側面はあっただろうが、自主ギャラリー出身の若い写真家は実際にはカメラ雑誌で次々とデビューしていった。それを目標としていた者も少なからずいただろう。ここに彼らの本音が見え隠れして、興味深くもある。
カメラメーカーには多くの写真愛好家を組織する団体(ニッコールクラブなど)の存在があったし、カメラ雑誌にはいまでは考えられないくらい多くの読者がいた。カメラ雑誌は当然ながらカメラメーカーからの広告を主な収入源として成立していた。こんな写真大国はほかにはない。
つまり、カメラメーカーとカメラ雑誌との関係と自主ギャラリーもまた無縁ではなく、切り離して考えることはできないだろう。1976年に新大久保に「プリズム」が開設されたが、最初の写真展紹介がはやくも『アサヒカメラ』(1976年6月号)に掲載されている。
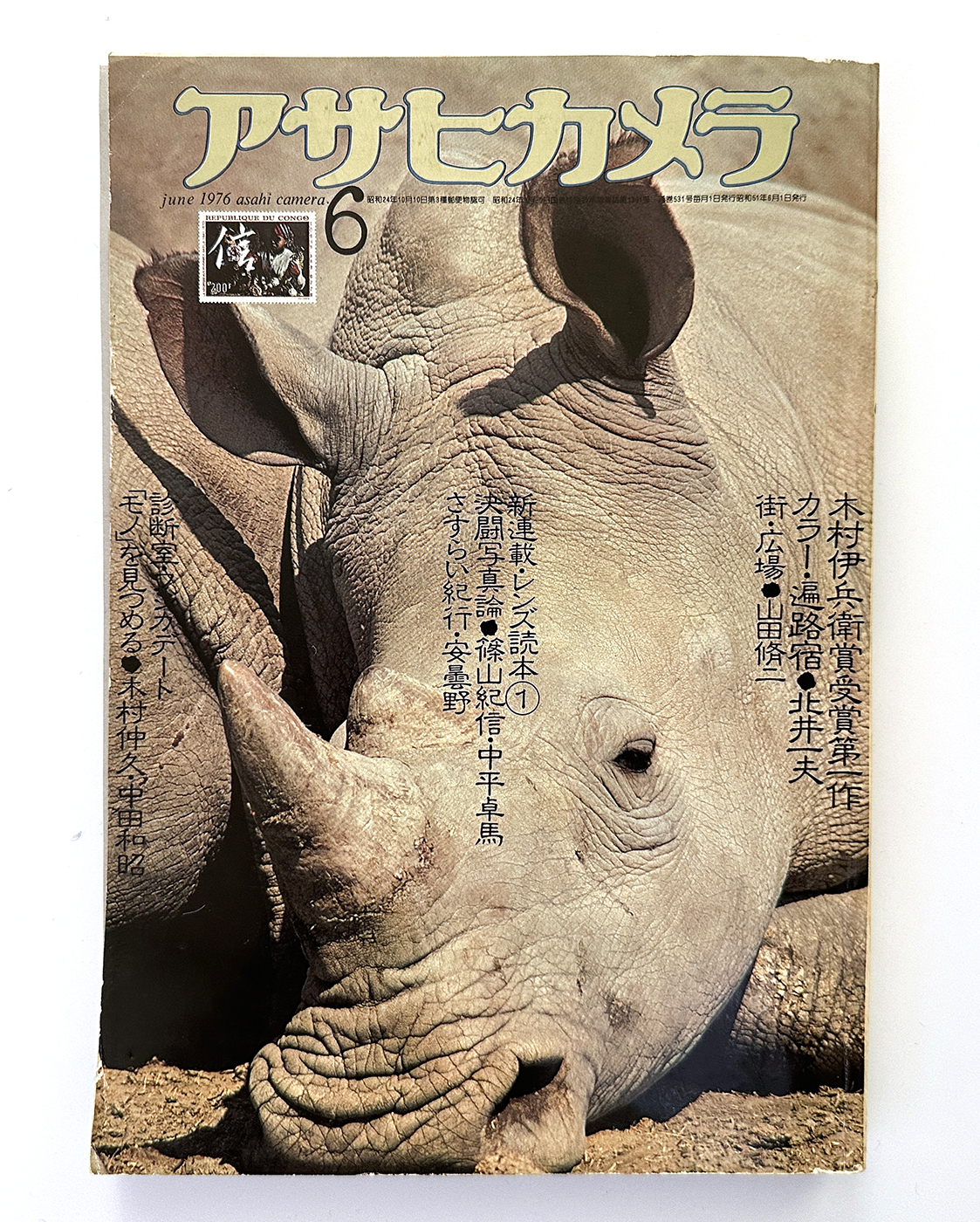
『アサヒカメラ』(1976年6月号)
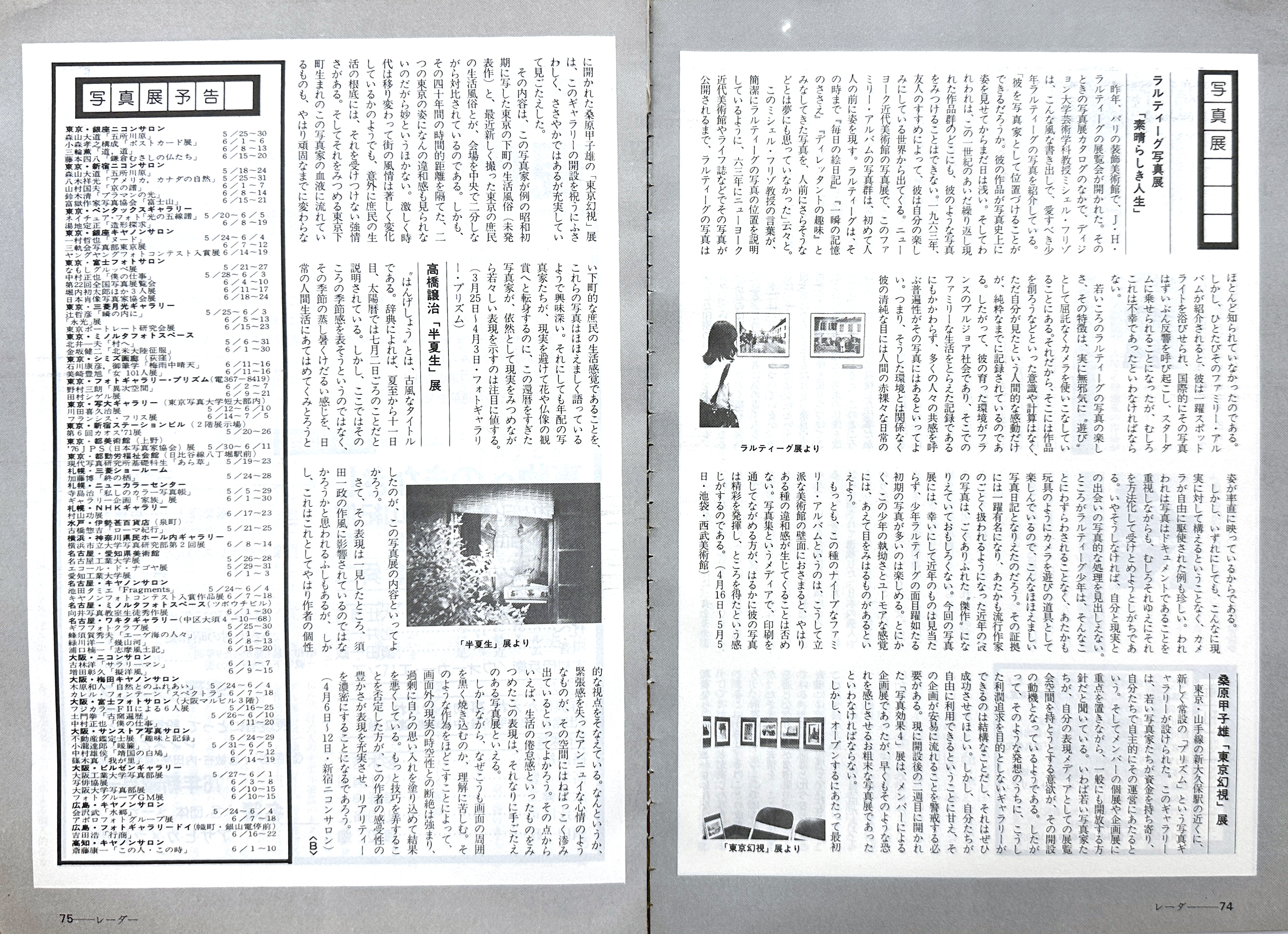
反メジャー指向、あるいはアンチであった若者もまた自覚、無自覚かは別として、間接的にカメラメーカーという巨大組織、巨大資本と深く関わっていたといえるだろう。
現在、私が危惧しているのはコロナ禍においてのメディアの喪失だ。歴史あるカメラ雑誌の『アサヒカメラ』『日本カメラ』が相次いでなくなってしまった。「ニコンサロン」は2020年に銀座と大阪から消えた。発表するメディアをいくつも突然失い、写真を撮る者は何を目標とすればいいのか。Web媒体への流れというはもちろんあるだろうが、紙媒体と場所の喪失は大きい。

最終号となった『アサヒカメラ』2020年7月号と『日本カメラ』2021年5月号
ただそのことにより、逆に自主ギャラリーが再認識、再注目され、これまでとは違った価値を持つのではないかと私は考えている。出版界全体が斜陽といわれているなかで、逆に紙の写真集がたとえ高価であっても再評価(若者からの注目度の高さも含め)され価値があがっていることを考えると、それほど見当違いなことではない気がしている。


PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。
ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。
今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。
 「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け
「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント
書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント