コラム
落合憲弘
John Sypal
タカザワケンジ
なぎら健壱
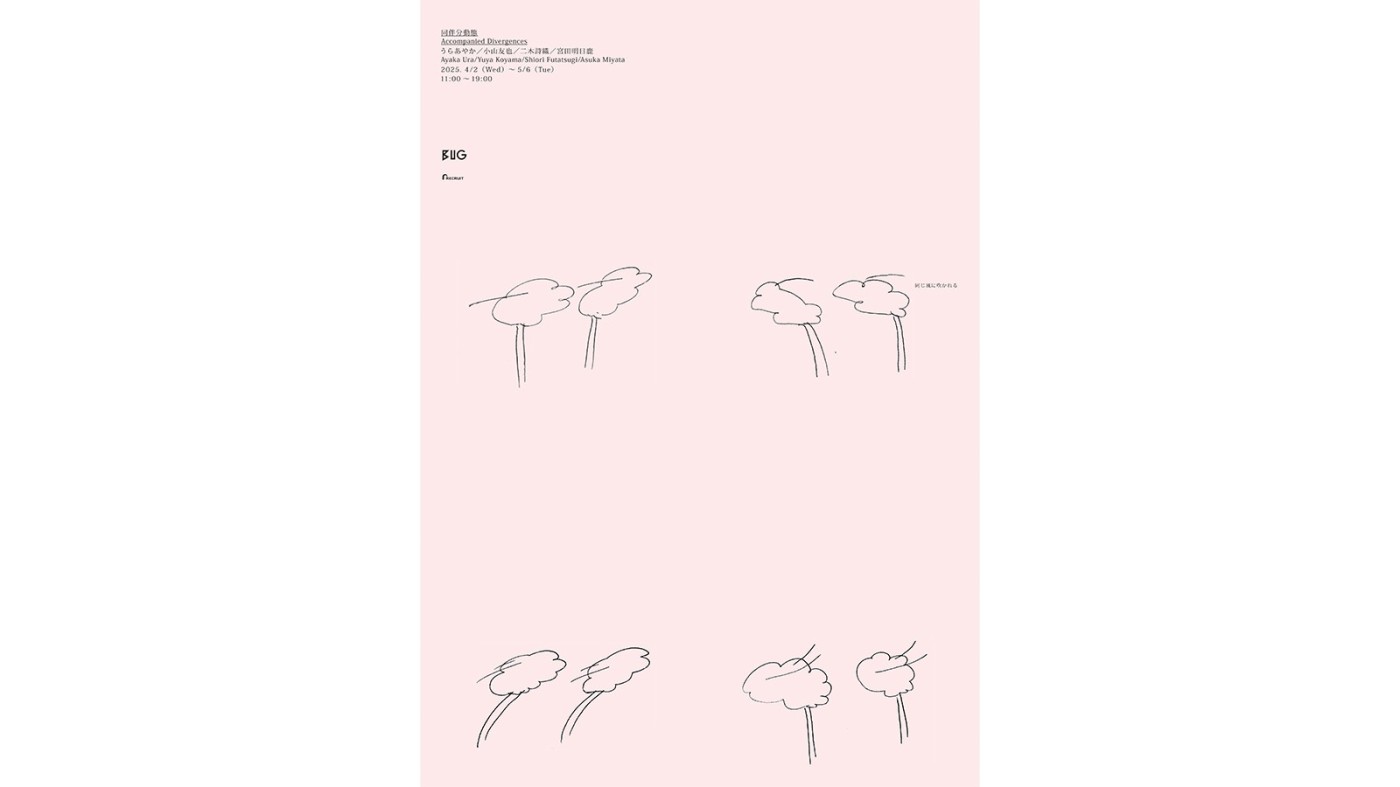
東京丸の内のアートセンターBUGで「同伴分動態」が開催される。
うらあやか、小山友也、二木詩織、宮田明日鹿の4名のアーティストによる、作品の展示やイベントとなる。展示スペースには、ワークショップ用スペースや小さな農園、カームダウン・クールダウンスペースなどを設ける。
うらさんとの出会いにより、本展は生まれました。
BUGはステートメントで、「無数のハプニングに、私たちは出会いたい」と掲げています。また、展覧会に限らない活動を展開していきたいという意志から、「アートセンター」を冠しています。その実現に向け、BUGではオープン前の2022年から、複数のアーティスト/アートワーカーと意見交換する機会**を設けてきました。うらさんもそのうちの一人であり、おもしろい場をつくることやアートマネジャーの職能などについて、ディスカッションを重ねてきました。今回は、そのやり取りから生まれたものを展覧会やイベントとして、ひらく試みです。
本展に参加する4名のアーティストは、作品をつくることはもちろん、制作で培った技術をコミュニティの運営や他者の表現のサポートなど、さまざまな活動に展開してきました。今回はその技術を活かして、だれかと一緒に何かをするときに働く力学に注目した作品の展示やイベントを行います。アーティストや来場者が「一緒に行動する」機会を創出することで、同伴しながら何かを生み出すことの可能性や、アートセンターのあり方を探索していきたいと考えています。
コ・キュレーション:うらあやか、野瀬綾(BUG)
■展覧会名に込められた意味
同伴分動態とは、「同伴」「分動」「態」の三つの言葉を組み合わせた造語。ある人たちが居合わせ、同伴しながら、それぞれが分かれて自由に動く、態(様子、ありさま)を意味する。本展に参加するのは、生活介護事業所*美術教育機関などで働きながら制作に取り組んでいるアートワーカー、アーティストだ。他者の表現活動のサポートや、学び合うことを通して、作者とその表現の間にはさまりながら生活を営む経験は、作品のアイデアや形態と結びつける。
■同伴することで生まれた それぞれの新作を展示
「同伴分動態」では、4名のアーティストがそれぞれの新作を出展する。アーティストたちは、「同伴しながらこしらえる技術」──ワークショップや職場、展示室といった複数人が集まる状況から作品を起動させること──を出発点として、作品の制作発表およびイベントを行う。
うらあやかは、他者や他の生物との関わり合いを軸に、参加型のパフォーマンス作品を主に制作してきたアーティストだ。今回は、2名のパフォーマーがボディランゲージを使って、「世界をよい方向に変えるためのアイデア」をやり取りするパフォーマンス作品を発表する。会場で希望者は、観るだけでなくパフォーマンスに参加することも可能。参加という形で作品への干渉をひらく背景には、鑑賞というコミュケーションへの、うらの期待が潜んでいる。また毎週水曜は、来場者とテーブルを囲んで「一緒に何かをやってみるイベント」が行われる。これは会期中を通して変化し続ける、実験的な取り組みといえる。このような取り組みは、これまでも観客(その場に居合わせた人)との協働によって成立する作品を発表してきた、うららしいアプローチだ。また同時に、鑑賞者は展覧会において「同伴者」として関係を結ぶ相手である、という意志の表れでもある。
小山友也は、ものや風景、社会システムなど無生物との間にあるコミュニケーションを、自身の身体を通して観察するパフォーマンス、ドローイング、映像作品を制作してきたアーティストだ。本展では、小山があるアートセンターに乗り込み、そこで働くスタッフから護身術で「制圧」される映像作品を展示する。作品や展覧会を守るため、不測の事態を静かに待つ看視スタッフの働きの誇張──スタッフによる護身術によって作家自身が制圧される──により、相対するふたつの身体は、あるひと続きの構造として可視化される。そのほかにも、オルタナティブな美術教育施設の「裏方」として運営に携わってきた人たちへのインタビューの記録や、BUGスタッフと共作した標語などを見せる。それらの作品は、周辺のものとして見落とされがちな、ある作品が生まれるまでの過程や作品が存在する空間、その空間を運営する人々に着目してつくられた。
二木詩織は、映像や対話を用いた作品の制作を通して、目の前で起きたことに対する感覚を部分的に増幅させることを試みてきた。本展では、自身が週5日間働く、生活介護事業所の様子やそこに通う人々との関わりを映像や写真で展示する。映像では、事業所を利用する方々が絵や刺繍、手織りなどを創作する光景や、事業所恒例の散歩の様子がとらえられ、そこには人々のやり取りや会話、距離感が映し出される。一方でこの作品を見る人は、そこに可視化されないもの、例えば、その会話が生まれるまでの積み重ね、個々の心境などにも思いを馳せることになるかもしれない。二木は作品を制作するにあたり、参加者の許可を丁寧に取りながら進めてきた。そのコミュニケーションのプロセスや、これまでに築かれてきた関係性などが作品には反映されている。また会期中には、事業所の利用者と支援員を会場に招き、作品鑑賞日を設ける。その際、事業所の人々には壁面の一部に「これからやりたいこと」を書き込んでもらう予定だ。
宮田明日鹿は、編み物の手法を用いた作品の制作や、手芸をしたい人が集い、学び合う場をつくる「手芸部」のプロジェクトを国内各地で行っているアーティストだ。今回は、農業用ネットを編み物で制作した大きなインスタレーションと、会場内でのスナップエンドウの栽培、堆肥を作る分業風景の映像作品などを展示する。6年前から家庭菜園をもつ宮田にとって、野菜を育てることは生活の中で大きな割合を占める営みだが、作品として表現することは初の試みだ。宮田は昨年から、生活と作品に共通するリサーチとしてコンポスト学校に通い始めた。そこで起こる生命の円環──人間の出した生ごみが微生物の働きによって堆肥になり、それを用いて野菜を育てる──から、「わけあうこと」や「ともに生きのびること」について考えを巡らせ、制作を続けている。また会期中には、「ネットのようなものを編む日」「スナップエンドウを採る日」を設け、宮田の営みや活動を展開する。
そのほか会場内には、出展アーティストとBUGスタッフの野瀬が書いた日記をまとめた冊子を配架する。この日記を書く取り組みは、うらからの呼びかけにより始まった。2021年から自身のブログを公開しているうらにとって日記は、目の前で起こっていることを基にイメージを膨らませたり、過去を想起して自由に実験のできる公開スタジオとして機能してきた。今回、5名の日記には、作品制作のプロセスやモヤモヤとした悩み、ついつい考えてしまうことなどが綴られる。作品と日記が同じ空間に並置されることで、鑑賞する方々も発想の過程に同伴・分動し、作品の多層性を感じるだろう。
- ■展覧会情報
「同伴分動態」
会期:2025年4月2日(水)~5月6日(火)
時間:11:00〜19:00
休廊日:火曜日(※ただし5月6日は開館)
会場:アートセンターBUG
住所:東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー1F
■イベント・パフォーマンス・ワークショップ実施日
▼うらあやかによる「毎週水曜アマチュアの会(名称仮)」
4月2日(水)、9日(水)、16日(水)、23日(水)、30日(水)時間未定
(現地開催、予約不要、参加費無料)
毎週水曜はうらあやかが在廊し、来場者やゲストと話したり、やってみたいことを試す会を開催する。
▼うらあやか作品のパフォーマンス実施日
4月4日(金)、5日(土)、6日(日)、11日(金)、12日(土)、13日(日)、18日(金)、19日(土)、20日(日)、27日(日)、5月2日(金)、3日(土)、4日(日)、5日(月)
※金曜、土曜、日曜、祝日の13:00-19:00の間、パフォーマンスは不定期に行われる。
▼出展アーティスト4名によるトークイベント
4月4日(金)19:00〜20:30
(現地開催、予約必須、参加費無料、後日アーカイブを配信)
作品制作のプロセスや展示作品の内容、また会場で公開しているそれぞれの日記のことなどを話す。
▼宮田明日鹿×橋本力男によるトークイベント
4月26日(土)14:00〜15:30
(現地開催、予約必須、参加費無料)
堆肥・育土研究所の代表、および有機農業者として三重県でコンポスト学校も主宰している橋本力男さんをゲストに招き、宮田明日鹿とトークを行う。現在、宮田が橋本さん主宰のコンポスト学校に参加していることから、今回のイベントが決定した。作品を起点に、堆肥、コンポスト、有機農業、オーガニックフラワーのお話などもお伺いする予定。
▼宮田明日鹿による「スナップエンドウを採る会」
4月24日(木)時間未定
(現地開催、予約不要、参加費無料)
会期中に展示会場内で栽培するスナップエンドウを宮田さんと採り、任意で食する会。
※スナップエンドウの生育状態次第では、内容が変更になる可能性がある。
▼宮田明日鹿による「ネットのようなものを編んでみる会」
4月25日(金)時間未定
(現地開催、予約不要、参加費無料)
家庭用編み機や糸を用いた作品を発表しながら、複数の地域で手芸部を企画運営する宮田と、展示会場で編み物を行う会。アーティストと話しながら、それぞれのペースで編み物に取り組んでいく。編み物未経験者の参加も大歓迎。
■プロフィール
うらあやか Ayaka URA

1992 年神奈川県生まれ。
主体性や責任の移動に関心をもち、参加型のパフォーマンス作品を多数制作。近年の個展に「マルチタスク」(武蔵野美術大学gFAL、東京、2023年)、「貝の/化石が/跡を残して/ 化石の/雌型/となった/身体」(金沢芸術村PIT5、石川県、2021年)。グループ展に「勝手に測る、挟まる、抜け出す」国際芸術祭「あいち2022」(愛知県美術館、名古屋、2022年)などがある。
https://urayaka.jimdofree.com/
https://www.instagram.com/urayaka/
小山友也 Yuya KOYAMA

1989年埼玉県生まれ。
交感の方法を分析・抽出・転用し、既存の枠組みに従属している身体の可視化と侵食を行い、未来と自由を模索します。近年の活動に、「S A Y O N A R A - M a r k Ⅱ」(TOYOTA MarkⅡ、東京、2021年)、「勝手に測る、挟まる、抜け出す」国際芸術祭「あいち2022」(愛知県美術館、名古屋、2022年)、「石_鑑賞と使用のための連続講座」(CSLAB、東京、2023年)などがある。
https://yuyakoyama.net/
https://www.instagram.com/yuya_koyama_/
二木詩織 Shiori FUTATSUGI

1993年神奈川県出身。武蔵野美術大学修士課程美術専攻油絵コース修了。
自身の体験をどう切り取るか、または編集するかをテーマにパフォーマンスや映像作品を手掛ける。
2019年から坂口佳奈と共に坂口佳奈+二木詩織として作品発表を継続している。
近年の展示に、「RENEWAL NEWREAL 二木詩織/山本篤」(Art Center Ongoing、東京、2022年)、「そこら中のビュー」(坂口佳奈+二木詩織)(Gallery PARC、京都、2023年)、「Oozing Point -滲み出る地点-」(鹿児島県三島村硫黄島、2023年)がある。
https://www.instagram.com/malmolko/
宮田明日鹿 Asuka MIYATA

1985年愛知県生まれ。桑沢デザイン研究所ファッション科テキスタイル専攻修了。
テキスタイル、ファッション、手芸、美術の領域を横断しながら、改造した家庭用電子編み機、手編みなどの技法で作品を制作。歴史的背景を参照しながら、手を動かすこと、人についてリサーチを重ね、顧みることなく継承されてきた習慣や風習に疑問を投げかける。手芸文化を通して様々なまちの人とコミュニティを形成するプロジェクトを各地で立上げている。近年の主な展覧会に、国際芸術祭「あいち2022」(愛知、2022年)、「ひらいて、むすんで」(岡崎市美術博物館、愛知、2024年)。手芸部プロジェクトに、「港まち手芸部」(愛知、2017年~進行中)、「金石手芸部」(石川、2021年)、「有松手芸部」(愛知、2022年)、「本町手芸部」(石川、2024年~進行中)など。
https://asukamiyata.com/
https://www.instagram.com/asukamiyata/?hl=ja
【関連リンク】
https://bug.art/exhibition/accompanied-divergences-2025/
| 出展者 | うらあやか、小山友也、二木詩織、宮田明日鹿 |
|---|---|
| 会期 | 2025年4月2日(水)~5月6日(火) |
| 会場名 | BUG |
※会期は変更や開催中止になる場合があります。各ギャラリーのWEBサイト等で最新の状況をご確認のうえ、お出かけください。


PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。
ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。
今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。
 「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け
「Photo & Culture, Tokyo」最新の更新情報や、ニュースなどをお届けメールマガジンのお届け 書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント
書籍、写真グッズなど会員限定の読者プレゼントを実施会員限定プレゼント